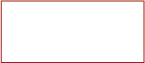Awards
Call for applications(Book Category)
Introduction of award-winning works[2023]
2023年度日本経営学会賞(論文部門)研究奨励賞
髙橋宏承
「組織構成員の外向性と組織内孤立の関係性」(『日本経営学会誌』第52号掲載)
 ● 受賞理由
● 受賞理由
日本型雇用システムの変容がみられる中、近年ではリモートワークの普及なども加わり、組織構成員の組織に対するコミットメントも変化しつつある。一方で、組織での心的要因により長期にわたる休養を余儀なくされる組織構成員が多いことも課題となっている。
当該論文は、既存の組織研究の多くが主観的な知覚である孤独感を対象としていたのに対し、客観的な状態である孤立に焦点を当て、マルチエージェント・シミュレーションという分析手法を用い、エージェントの行動と相互作用の結果によって孤立が起こるプロセスを分析した独創的な研究であり、学術的にも実践的にも意義のあるものといえる。
分析結果は、1)高外向性構成員数の多い組織ほど孤立構成員数が多くなる、2)組織内の孤立構成員数は基本的に低外向性構成員数に依存している、3)最長孤立期間の構成員は高外向性構成員である、という興味深い3 点を導き出し、ある意味で逆説的なインプリケーションともいえ、既存の研究に対する当論文の独自性を浮き彫りにするものといえる。
モデル設定における現実妥当性の問題等、論者もいくつかの限界を述べているが、経営学を科学に近づけるための研究のひとつともいえ、今後の経営学の進化という点から見れば、当論文の挑戦は評価すべきものと位置づけられる。以上の評価から、当論文は、日本経営学会賞論文部門の研究奨励賞を授与するに充分な価値を有しているものと判断される。
●受賞挨拶
千葉大学 髙橋宏承
この度は日本経営学会賞(論文部門)研究奨励賞に選出いただきまして、誠にありがとうございます。審査委員長の鈴木由紀子先生をはじめ、委員の先生方や査読を担当してくださった匿名のレフェリー2名の先生方、そして学会賞セッションにてお世話になった出見世信之理事長には、心より感謝申し上げます。
本研究は、既存研究で主に注目されている孤独感ではなく、より客観的な状態を表す孤立概念に着目し、組織構成員の外向性と孤立の関係性を明らかにしようと試みたものです。組織内での孤立は個人の多様な成果に影響を及ぼしますが、孤独感の研究と比べて十分に研究が蓄積されていませんでした。また、特に重要な先行要因として考えられる外向性との関係も明らかになっていないという課題が残されていました。これは、孤立という客観的な状態をデータとしてとらえることの困難性の問題に由来する部分があります。本研究ではネットワーク論の視座からマルチエージェント・シミュレーションの手法を活用し、データを収集・分析することで、その問題の克服に挑戦しました。本研究で得られた結果の一つは、外向性の高い組織構成員の方が孤立しやすいというものです。これは外向性に関連するコミットメントやコミュニケーション相手の多様性が関与していると解釈できます。一般的に、外向性の高い人は孤独感を感じにくく、孤立しにくいと認識されていますが、むしろ外向性の高い構成員に対して組織は特に注意を払う必要があることが本研究の結果から示唆されます。
今後、孤立研究をさらに発展させるために、外向性以外の個人特性や職務・組織特性を先行要因とした研究が期待されます。また、方法論的には、他のデータとシミュレーション・データを組み合わせ、より発展的な分析を試みることも考えられます。AIの導入やリモートワークの普及によって、今後さらに重要なテーマとなると考えられる孤立研究において、本研究がその一助になれば幸いです。
最後に、学生時代から指導いただいている沼上幹先生や島貫智行先生、学内外の研究会などでアドバイスをくださった皆様に、この場を借りて改めて深く感謝申し上げます。今回の受賞を励みに、今後も研究に一層精進してまいります。誠にありがとうございました。
List of Recipients of the Japan Academy of Business Administration Awards
▶Book Category
| 2023年度 | なし |
|
| 2022年度 | 松尾 健治 | |
| 2021年度 | 藤岡豊 | 『⽣産技術システムの国際⽔平移転─トランスナショナル経営の実現に向けて─』(有斐閣) |
| 2020年度 研究奨励賞 |
兒⽟公⼀郎 | 『業界⾰新のダイナミズム−デジタル化と写真ビジネスの変⾰』(⽩桃書房) |
| 2019年度 研究奨励賞 |
松本 雄一 | 「実践共同体の学習」(白桃書房) |
| 2018年度 | 高井 文子 | 『インターネットビジネスの競争戦略:オンライン証券の独自性の構築メカニズムと模倣の二面性』(有斐閣) |
| 2017年度 | 宮尾 学 | 『製品開発と市場創造: 技術の社会的形成アプローチによる探求』(白桃書房) |
| 2016年度 | 山田仁一郎 | 『大学発ベンチャーの組織化と出口戦略』(中央経済社) |
| 2015年度 | なし | |
| 2014年度 | なし | |
| 2013年度 | 長山宗広 | 『日本的スピンオフ・ベンチャー創出論─ 新しい産業集積と実践コミュニティを事例とする実証研究─』(同友館) |
| 2012年度 | 加藤俊彦 | 『技術システムの構造と革新─方法論的視座に基づく経営学の探究─』(白桃書房) |
| 2011年度 | なし | |
| 2010年度 | なし | |
| 2009年度 | 李東浩 | 『中国の企業統治制度』(中央経済社) |
| 2008年度 | 岩田智 | 『グローバル・イノベーションのマネジメント─日本企業の海外研究開発活動を中心として─』(中央経済社) |
| 藤田誠 | 『企業評価の組織論的研究─ 経営資源と組織能力の測定─』(中央経済社) | |
| 2007年度 | なし | |
| 2006年度 | 川上智子 | 『顧客志向の新製品開発─マーケティングと技術のインタフェイス─』(有斐閣) |
| 2005年度 | なし |
▶Research Paper Category
| 2023年度 研究奨励賞 |
髙橋宏承 | 「組織構成員の外向性と組織内孤立の関係性」(『日本経営学会誌』第 52 号掲載) |
| 2022年度 |
内田大輔・
芦澤美智子・ 軽部大 |
「アクセラレーターによるスタートアップの育成―日本のアクセラレータープログラムに関する実証分析―」(『日本経営学会誌』第 50 号掲載) |
| 2021年度 | 平野恭平・ 三井泉・ 藤田順也 |
「経営学部創設期の「落書き」による学生たちの心性史試論-神戸大学附属図書館蔵書を一例として」(『日本経営学会誌』第48号掲載) |
| 2021年度 研究奨励賞 |
林侑輝 | 「逆境期における長寿企業の生存戦略-倒産企業との比較分析に基づく類型化」(『日本経営学会誌』第47号掲載) |
| 2020年度 研究奨励賞 |
柴野良美 | 「組織⽂化が企業不正に与える影響−企業理念のテキストマイニングを⽤いた定量的実証研究」(『日本経営学会誌』第 45 号掲載) |
| 2019年度 | 林祥平・ 森永雄太・ 佐藤佑樹・ 島貫智行 |
「職場のダイバーシティが協力志向的モチベーションを向上させるメカニズム」 |
| 2018年度 | 加藤崇徳 | 「技術多角化と技術の時間軸」(『日本経営学会誌』第 38 号掲載) |
| 2017年度 | なし | |
| 2016年度 | 西岡由美 | 「契約社員の人事管理と基幹労働力化―基盤システムと賃金管理の二つの側面から―」(『日本経営学会誌』第36号掲載) |
2015年以前の対象は45才以下の会員による執筆論文
2015年以前の履歴については学会ニュースをご参照ください